恋と友情の話というとどちらかというと青春的な、いい話なのかと思う人が多いだろう。 頭に「盲目的な」というやや不穏な形容詞はついているものの、通常この言葉がかかるのは「恋」の方であり、ただそれだけならよくある話でしかない。 しかしこの作品は、山本文緒氏の解説でも述べられている通りかなりダークな内容であり、そしてこの作品の真価は(前半の恋パートももちろん良い出来なのだが、僕が思うにはそれ以上に)後半の「盲目的な友情」の方である1。
タカラジェンヌを母にもち、自身も周りから「“キレイな子"なんていうレベルを超えている」と評されるほどの美貌を持つ(が本人はどうやらその自覚があまりない)蘭花は、大学入学時に入部した学生オケでプロの指揮者をしている茂美と出会う。 入学当初は茂美は先輩部員と付き合っているも同然の状態であり、蘭花も「告白してくれたから」という理由だけで同級生と付き合ったりもしていたが、やがて二人惹かれ合うようになり、蘭花の二年次に交際を始める。 しかし茂美にはとある秘密があった。 明るく周りに対し面倒見のよい性格で、合コンにもよく行き恋愛にも積極的な美波や、容姿に強いコンプレックスを抱いているも幼少期から続けているバイオリンは部員皆から認められる腕前の留利絵といったオケの友人たちとの人間関係模様も交えながら、蘭花の恋は泥沼の展開を迎える……。
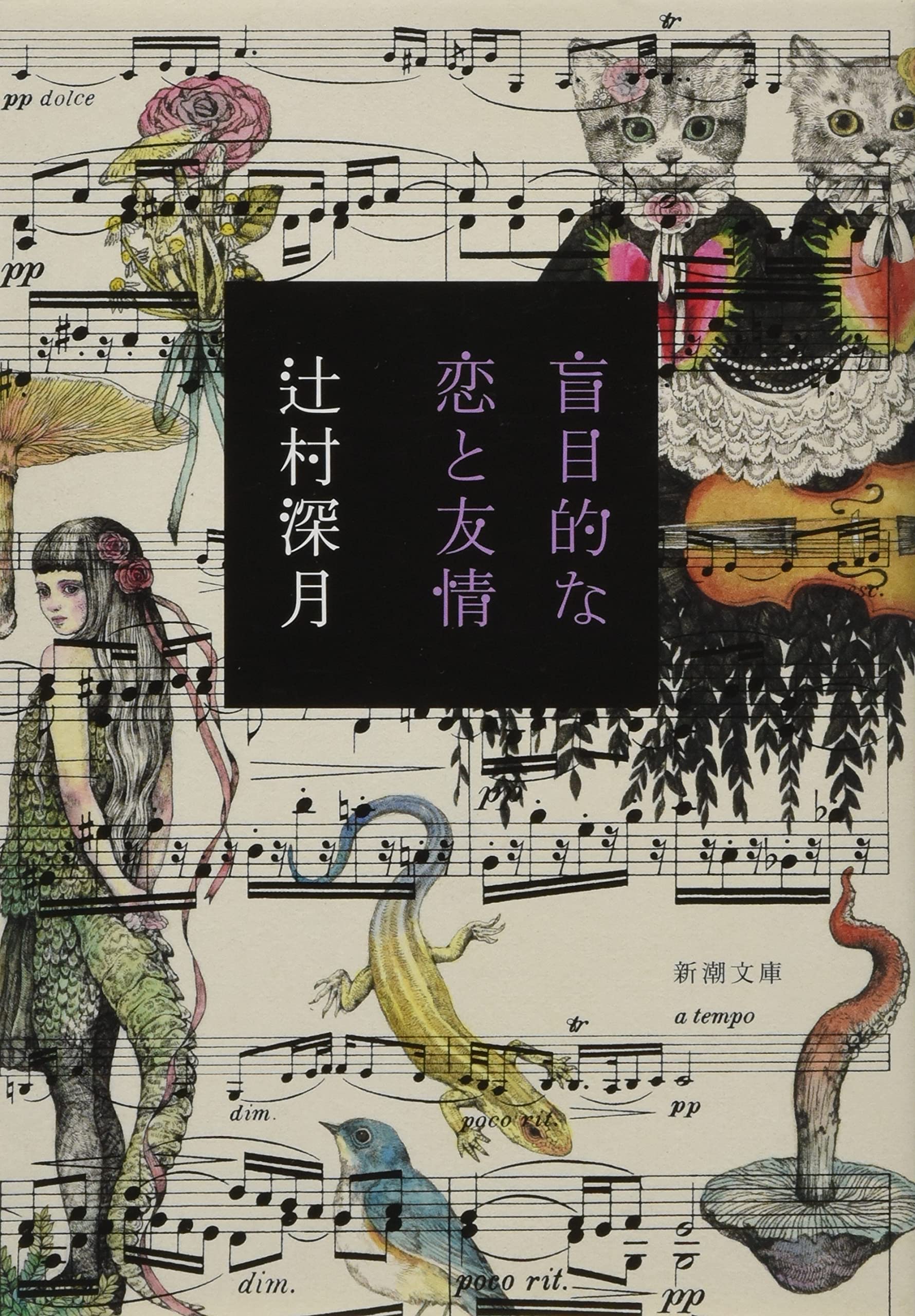
というのは蘭花が語り手となる前半の「恋」パートであり、後半の「友情」パートでは、その蘭花をそばから見続けた留利絵視点の同時系列の話となる。 二人目の主人公なのだからあらすじも留利絵が重要人物となるように書くべきなのだが、蘭花を中心に据えた書き方ではそれを上手く書くことができない。 だがこの作品ではそのようなあらすじになってしまうのが道理で、なぜなら蘭花にとって留利絵は多数いる友人のうちの一人に過ぎないためである。 そして、一方の留利絵はそう思ってはおらず、蘭花を"互いにとって"唯一無二の親友でなければならない存在と考えている。 その留利絵の話こそが、後半の「盲目的な友情」の話となる。
留利絵は幼少期からひどいニキビに悩まされており、小学生の頃に同級生の男子にからかわれ(それを女子に笑われた)経験も相まって容姿に強いコンプレックスを抱いている。 進学校に進んだ中高では理解のある友人をもてたものの、大学に進学して環境が変わって学生オケに入ると、軽率な態度を見せる男子部員や、バイオリン未経験でありながら部内で上手くやっている美波を見て、再び小学生の頃の記憶を思い出すようになる。 そんな中で留利絵が心の拠り所とするのが、非常な美貌を持ちながらそれを鼻にかける態度を一切見せず、音楽や芸術といった文化的に"洗練された"趣味の話もできる蘭花の存在だった。 コンマスを決める際の話など、いくつかの出来事の中で留利絵は美波に対して嫌悪を強く抱くようになりながら、蘭花との友情を盲目的に追い求めるようになっていく。
留利絵は作中で美波や他の男子からバカにされていると繰り返し語るが、不可解な言動を取っているのも、上手くやっている美波を内心馬鹿にして見下しているのも明らかに留利絵の方だし、その語りを読まされる読者から見るとその姿は非常に痛々しい。 だが一方で、自分を見下して笑っている(と本人は感じている)相手を「軽薄だ」「わかっていない」と見下し返すことで自身の心を守ろうとする態度は理解できてしまう面もあるし、実際身に覚えのある人も多いと思う2。 しかも留利絵は自身の嘘を取り繕おうと振る舞っているものの、美波にはその態度は完全に見破られているのでさらに痛々しさは増している。 本書の「友情」パートでは、誰の中にもある3、そうした自身と合わない人を見下すことで自身を保とうとする自分の態度を、一人称視点の留利絵の語りを鏡として見せつけられる。 そこがこの本を読んでいて自分にとって辛いところであり、この読書体験の価値であった。
プロローグでも触れられている通り、茂美は作中で亡くなり、蘭花は別の男性と結婚式を挙げることになる。 この茂美の死についてももちろん秘密があって、それに関する予想は最後で裏切られ、そしてこの結婚とも関わる結末の真相にも震撼させられる。 本書を未読でこのブログを読んでいる方が1人でもいる可能性が1ミリでもあることを考えるとそれについてはこれ以上書けないのだが、自分的にはこの終わり方は後味が悪く、(僕がこれまで思っていた)辻村深月らしくなくて良いと思った。 どちらかというと辻村深月は良い話として締めることが多く、そのまとめ方にやや強引さを感じた作品もあったこともあり、救いのない終わり方をする作品の後味の悪さを読後感として味わうことが好きな自分は少し合わないと感じるところがあった。 しかしこの作品はその結末の真相もあいまって非常に後味悪い締め方をしており、その読後感も含めて自分がこれまで読んできた辻村深月数作の中では一番自分に合うと思う小説だった。
余談だが、巻末の山本文緒氏の解説も非常によく書かれている、というかよく書かれ過ぎている。 自分が感じた点が適切に言語化されてしまっていて、この感想ブログを書いていてもその解説をなぞるようになってしまったところもあるかもしれない。 自分自身の感想の言語化にならないので、うまく書かれている解説ほど自分で感想を書き記し終えるまでは先に解説を読んではいけないなと思った。
-
と思うのは、異性からはもちろん同性からも羨まれるほどの美貌を持ちながら自分はそのことに自覚が薄く、かつ性格は浮世離れている(というか世間知らずというか)ところのある前半の恋パートに蘭花に、自分は自身を重ねることが出来なさ過ぎて感情移入しきれなかったことも理由の一つかもしれないが。 ↩︎
-
一般的に言ってみて取り繕おうとしているが、懺悔しながら率直にいうと、要するに僕自身にそういう面がある(あった)ということである。 ↩︎
-
いや作中の蘭花のような人間は(もしいたとするなら)そのような感情は抱かないのかもしれないが、その「善良さ」は蘭花の浮世離れ度あるいは世間知らず度と表裏一体のものであり、前に読んだ同作者の『傲慢と善良』で語られる「善良さ」にもある種で通じるのかもしれない。 ↩︎